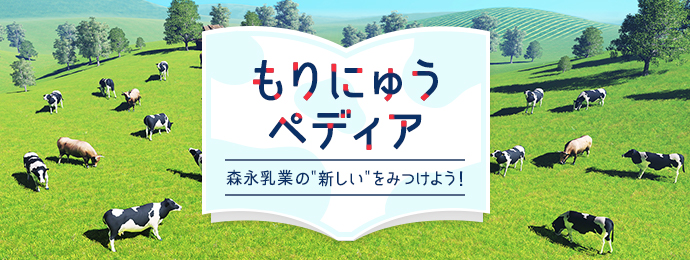LESSON 4
ヒトにとってベストコンビといえる
ビフィズス菌とは?
ビフィズス菌とひと口に言っても実はその種類はさまざま。
では、私たちの健康にとって重要な役割を果たしてくれるビフィズス菌とはどのような種類なのでしょうか?
特定のビフィズス菌だけがヒトと
1500万年前からチームメイト!?
- ビフィズス菌はいつから僕たちのおなかに棲んでいるのですか?
- ヒトがゴリラやチンパンジーと分かれて進化する以前からです。ビフィズス菌とヒトは、非常に長い間共に生き、共に進化してきた間柄なんです。
生存競争で勝ち残れたのは、
ビフィズス菌のおかげ......?
read more
ビフィズス菌はヒトの祖先にあたる類人猿が出現した頃、おおよそ1500万年前には既におなかの中に棲んでいたと考えられています。
類人猿が、ヒト、チンパンジー、ボノボ、ゴリラに分かれて進化してきた歴史の中で、いくつかの宿主を行き来しながらおなかの中に棲んでいる腸内細菌もいます。でも、ビフィズス菌は別。現代のヒトの腸で見つかるビフィズス菌はヒトの祖先にのみ、ゴリラの腸に棲むビフィズス菌はゴリラの祖先にのみ棲んでいたのです。それはなぜかというとビフィズス菌が宿主の腸内環境に適応するようそれぞれ別の種として進化してきたから。宿主の目線で考えると、ビフィズス菌を腸内に保有する個体が生き延びてきた結果と捉えることができます。これはヒトに棲んでいる種類のビフィズス菌こそがヒトの健康に重要な役割を担ってきた何よりの証拠であるとも言えます。1500万年もの長い歳月を共にしてきたのは、お互い共生するメリットがあったからこそ。特定のビフィズス菌はヒトと一つのチームとして共に進化し、厳しい生存競争を勝ち抜いてきたベストコンビなのです。
赤ちゃんの腸内のビフィズス菌へ、母乳から愛のパス!
- では、ヒトに棲むビフィズス菌とそれ以外のビフィズス菌は違う種類ということですか?
- その最も大きな特徴のひとつは「ヒト母乳との相性」 なんです。
健康な赤ちゃんの腸内は
ビフィズス菌でいっぱい......?
read more
健康な赤ちゃんのおなかにはたくさんのビフィズス菌が棲んでいることをレッスン3でお伝えしましたね。これは母乳との深い関係があるんです。
母乳には、赤ちゃんの成長に必要な栄養素や身体を守る抗菌活性物質が含まれているのですが、ヒトが利用できない「ヒトミルクオリゴ糖」と呼ばれるオリゴ糖もたくさん含まれています。これをビフィズス菌が優先的にエサとして利用しているため、健康な赤ちゃんの腸内はビフィズス菌がほとんどなんです。ところが、ヒトに棲んでいない種類のビフィズス菌は、この特殊なオリゴ糖を利用することができず、しかも母乳中に含まれるリゾチームという抗菌活性物質で死んでしまうんです。つまり、同じビフィズス菌の仲間でも赤ちゃんが進んでおなかに棲ませている菌と、バイ菌と同じように排除される菌がいるということなんです。
赤ちゃんがおなかにビフィズス菌をたくさん棲ませている理由は十分明らかにされていませんが、悪い菌から身体を守るだけではなく、免疫や脳など赤ちゃんの正常な発育に関与していると考えられています。
ビフィズス菌をキープし続けることが健康のもと!?
- そもそもですが、おなかにビフィズス菌が棲んでいるのに、外部からわざわざ摂取する必要はあるのでしょうか?
- ビフィズス菌は加齢や病気によって減少してしまうので、日々補い続けることが大事なんです。
元気なお年寄りの
おなかのなかは......?
read more
ビフィズス菌の量は、授乳中の赤ちゃんの時がピークで、成長とともに減少します。食事を含めた生活習慣や体質により個人差がありますが、青年期、中年期に腸内細菌に占めるビフィズス菌の割合は、平均でおおよそ10%程度。60〜70代頃からはさらに顕著に減少していきます。元気な高齢者と寝たきりの高齢者の腸内細菌を比べてみると、元気な人の方が腸内のビフィズス菌が多いという研究成果も。また、疾患により腸内のビフィズス菌が少なくなってしまうという報告も数多くあるんですよ。
だからこそ腸内環境は、私たちの長寿の鍵と言われています。おなかのビフィズス菌が元気に働けるよう食事のバランスに気をつけることはもちろん、毎日ビフィズス菌を補って常に腸内にビフィズス菌がいる状態をキープし続けることが大事です。私たちの健康に大きく寄与してくれるビフィズス菌は、元気に人生を過ごしたいと願う私たちにとって心強いサポーターなんです。